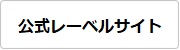- 著者 柳田 国男
- カバーデザイン 芦澤 泰偉
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2011年11月25日
- 判型:
- 文庫判
- ページ数:
- 272
- ISBN:
- 9784044083021
雪国の春 柳田国男が歩いた東北
- 著者 柳田 国男
- カバーデザイン 芦澤 泰偉
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2011年11月25日
- 判型:
- 文庫判
- ページ数:
- 272
- ISBN:
- 9784044083021
柳田国男が歩いた東北から日本を考える
名作『遠野物語』を刊行した一〇年後、柳田は二ヶ月をかけて東北を訪ね歩いた。その旅行記「豆手帖から」をはじめ、「雪国の春」「東北文学の研究」など、日本民俗学の視点から東北を深く考察した文化論。
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
もくじ
自序
雪国の春
『真澄遊覧記』を読む
雪中随筆
新交通
コタツ時代
風と光と
藁布団
センバ式文化
火の分裂
炭と家族制度
火の管理者
炭焼来る
夢は新たなり
折り焚く柴
旧文明のなごり
北の野の緑
草木と海と
名所崇拝
紀行文学の弊
松が多過ぎる
自由な花
鳥の極楽
砂浜の草
まいかいの紅
合歓と椿
槲の林のこと
風景を栽える
豆手帖から
仙台方言集
失業者の帰農
子供の眼
田地売立
狐のわな
町の大水
安眠御用心
古物保存
改造の歩み
二十五箇年後
町を作る人
蝉鳴く浦
おかみんの話
処々の花
鵜住居の寺
樺皮の由来
礼儀作法
足袋と菓子
浜の月夜
清光館哀史
津軽の旅
おがさべり──男鹿風景談──
山水宿縁
風景の大小
半島の一世紀
海の路絶えたり
本山真山の争い
正月様の訪問
二人の山の鬼
椿の旅
鹿盛衰記
雉の声
花と日の光
風景の宗教的起原
南北の結合
旅人の種類
東北文学の研究
一、『義経記』成長の時代
発端
『義経記』の成立
座頭の交通と割拠
読み本としての『義経記』
奥浄瑠璃の元の形
家と物語と
二、『清悦物語』まで
生き残った常陸坊
清悦出現のこと
『鬼三太残齢記』
『義経勲功記』
人魚の肉
八百比丘尼の事
九穴の貝
おとら狐と玄蕃丞
語り部の零落
盲目の力
注釈
解説 岡見 正雄
解説 新装にあたって 鶴見 太郎
雪国の春
『真澄遊覧記』を読む
雪中随筆
新交通
コタツ時代
風と光と
藁布団
センバ式文化
火の分裂
炭と家族制度
火の管理者
炭焼来る
夢は新たなり
折り焚く柴
旧文明のなごり
北の野の緑
草木と海と
名所崇拝
紀行文学の弊
松が多過ぎる
自由な花
鳥の極楽
砂浜の草
まいかいの紅
合歓と椿
槲の林のこと
風景を栽える
豆手帖から
仙台方言集
失業者の帰農
子供の眼
田地売立
狐のわな
町の大水
安眠御用心
古物保存
改造の歩み
二十五箇年後
町を作る人
蝉鳴く浦
おかみんの話
処々の花
鵜住居の寺
樺皮の由来
礼儀作法
足袋と菓子
浜の月夜
清光館哀史
津軽の旅
おがさべり──男鹿風景談──
山水宿縁
風景の大小
半島の一世紀
海の路絶えたり
本山真山の争い
正月様の訪問
二人の山の鬼
椿の旅
鹿盛衰記
雉の声
花と日の光
風景の宗教的起原
南北の結合
旅人の種類
東北文学の研究
一、『義経記』成長の時代
発端
『義経記』の成立
座頭の交通と割拠
読み本としての『義経記』
奥浄瑠璃の元の形
家と物語と
二、『清悦物語』まで
生き残った常陸坊
清悦出現のこと
『鬼三太残齢記』
『義経勲功記』
人魚の肉
八百比丘尼の事
九穴の貝
おとら狐と玄蕃丞
語り部の零落
盲目の力
注釈
解説 岡見 正雄
解説 新装にあたって 鶴見 太郎
「雪国の春 柳田国男が歩いた東北」感想・レビュー
-
民俗学創始者の東北旅行記。雑誌や新聞に発表されたものを中心としてまとめられているだけあり、民俗学というより随筆のように読めた。ただその中にも菅江真澄の事や椿の事、樺の皮を紙の代わりに使う事、失業者問題 …続きを読む2013年02月13日30人がナイス!しています
-
東北各地を巡る聞き取り調査を紀行文体で記しつつ、「東北学」の構想を立ち上げるに至る本書の各エッセイでは、現地の人々を観察する側に立つ自身が他者として関与する点を著者が強く意識していたことが実感できる。 …続きを読む2025年02月03日8人がナイス!しています
-
大正中期から昭和初期の主に東北地方の民俗について書かれた一冊。表題作『雪国の春』と『東北文学の研究』が特に心に残りました。私も雪国の豪雪地帯で生まれ育った身なので、雪国の冬の閉塞感とじっと春を待つ雰囲 …続きを読む2016年03月28日8人がナイス!しています