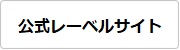- 著者 渡邉 裕美子
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2011年01月25日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 242
- ISBN:
- 9784047021501
歌が権力の象徴になるとき 屏風歌・障子歌の世界
- 著者 渡邉 裕美子
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2011年01月25日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 242
- ISBN:
- 9784047021501
屏風歌・障子歌はなぜ作られたか。一流の歌人や絵師を動員した芸術品に迫る
平安から鎌倉初期、当代一流歌人・絵師・書家によって作られたいくつもの屏風歌・障子歌。その発生から隆盛、衰退を経て一二世紀後半に社会情勢の変化とともに復活する様相を、和歌と権力の視点から描く。
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
「歌が権力の象徴になるとき 屏風歌・障子歌の世界」感想・レビュー
-
10世紀から11世紀後半、それなりに平和な平安の御代である。代表的なのは藤原道長の娘彰子が入内するとき、和歌を添えた大和絵の屏風が制作された。嫁入り道具である。和歌は当時の一流の作者に依頼された。財力がな …続きを読む2021年07月23日5人がナイス!しています
-
願わくば実物を見てみたい。2017年07月23日1人がナイス!しています
-
「歌が権力の象徴になるとき」というタイトルに惹かれ、政治社会学的観点からの記述を期待して読み始めたが、副題の屏風歌・障子歌の世界が示唆する如く文学史の本、全くの興味の対象外で、短時間の斜斜読にて終了。2011年07月25日0人がナイス!しています