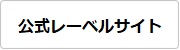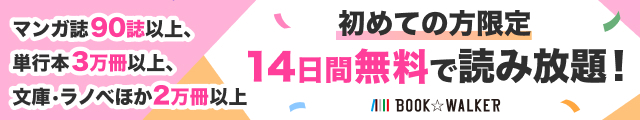- 著者 五味 文彦
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2012年05月23日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 368
- ISBN:
- 9784047035065
後鳥羽上皇 新古今集はなにを語るか
- 著者 五味 文彦
- 定価: 円 (本体円+税)
- 発売日:
- 2012年05月23日
- 判型:
- 四六判
- ページ数:
- 368
- ISBN:
- 9784047035065
後鳥羽はなにを「和歌の力」に頼んだか?新古今集成立の背景と史実を探る!
幕府討滅計画=承久の乱で知られる後鳥羽上皇は、なぜ『新古今集』の撰集にあれほどの心血を注いだのか。幕府の「武」に対し、これを圧倒する文化統治として「和歌の力」を位置づけた上皇の足跡と史実を描く。
〈目次〉
はじめに
1 激動の時代を経て
一 神器なしの王位
1 僥倖と欠落と
2 母乳をめぐる争い
3 天皇の成長
二 自立への道
4 入内争い
5 法皇の死
6 親政の展開
三 政治の激変
7 武家の上洛
8 脱兼実に向けて
9 親政から院政へ
2 王と和歌文化
四 後鳥羽院政
10 後鳥羽院政の展開
11 公武の衝撃
12 王の歌
五 百首歌を詠む
13 和歌をめぐる環境
14 通親を超えて
15 正治初渡百首
六 和歌を詠む喜び
16 定家と上皇
17 歌への意欲
18 光と影
七 勅撰集を見据えて
19 能力を見極める
20 勅撰和歌集の勅撰に向けて
21 撰集への動き
3 勅撰和歌集の構想
八 文化統合
22 院三度百首歌
23 和歌所の開設
24 熊野御幸に向けて
九 撰集の開始
25 熊野御幸と定家
26 撰者の指名
27 仏教界の嵐
十 目標を定める
28 撰集の指標
29 新たな和歌空間
30 水無瀬恋十五首歌合
十一 壁にあたる
31 千五百番歌合の達成
32 時代の変わり目
33 続く不幸と立ち直り
4 新古今和歌集の成立
十二 撰集の山場
34 和歌書の活動
35 関東の異変
36 俊成九十歳の賀
十三 新古今和歌集の成立へ
37 幕府と朝廷の関係
38 和歌所の撰集
39 編纂の最終段階
十四 新古今和歌集の奏覧
40 真名序の成立
41 奏覧と竟宴
42 仮名序と義経
おわりに
参考文献
〈目次〉
はじめに
1 激動の時代を経て
一 神器なしの王位
1 僥倖と欠落と
2 母乳をめぐる争い
3 天皇の成長
二 自立への道
4 入内争い
5 法皇の死
6 親政の展開
三 政治の激変
7 武家の上洛
8 脱兼実に向けて
9 親政から院政へ
2 王と和歌文化
四 後鳥羽院政
10 後鳥羽院政の展開
11 公武の衝撃
12 王の歌
五 百首歌を詠む
13 和歌をめぐる環境
14 通親を超えて
15 正治初渡百首
六 和歌を詠む喜び
16 定家と上皇
17 歌への意欲
18 光と影
七 勅撰集を見据えて
19 能力を見極める
20 勅撰和歌集の勅撰に向けて
21 撰集への動き
3 勅撰和歌集の構想
八 文化統合
22 院三度百首歌
23 和歌所の開設
24 熊野御幸に向けて
九 撰集の開始
25 熊野御幸と定家
26 撰者の指名
27 仏教界の嵐
十 目標を定める
28 撰集の指標
29 新たな和歌空間
30 水無瀬恋十五首歌合
十一 壁にあたる
31 千五百番歌合の達成
32 時代の変わり目
33 続く不幸と立ち直り
4 新古今和歌集の成立
十二 撰集の山場
34 和歌書の活動
35 関東の異変
36 俊成九十歳の賀
十三 新古今和歌集の成立へ
37 幕府と朝廷の関係
38 和歌所の撰集
39 編纂の最終段階
十四 新古今和歌集の奏覧
40 真名序の成立
41 奏覧と竟宴
42 仮名序と義経
おわりに
参考文献
※画像は表紙及び帯等、実際とは異なる場合があります。
「後鳥羽上皇 新古今集はなにを語るか」感想・レビュー
-
後鳥羽上皇が「新古今和歌集」を編纂するまでの経過を、当代の歌人を論じた「後鳥羽院御口伝」、側近の「源家長日記」、編者の一人藤原定家の「明月記」などを資料として読み解いています。著者の五味さんは「歴史家 …続きを読む2022年08月05日13人がナイス!しています
-
なぜ天皇という存在が続いたのかを考える時そのシステムに目が行きがちだが、政治も歴史も人間のつくるものなのだから一人一人の天皇の能力やキャラクターも考慮に入れるべきと気付いた。上皇は武士という新しい身分 …続きを読む2018年02月01日2人がナイス!しています
-
g069、大雑把に後鳥羽上皇というのは(天皇位にあった時よりも上皇位にあるほうが政治力が増すので院政敷いた人は上皇として呼ばれることが多い)、源平の争いの末に幼い安徳天皇が三種の神器と共に沈み、その代 …続きを読む2016年07月23日2人がナイス!しています